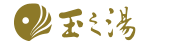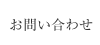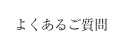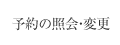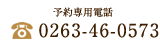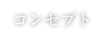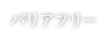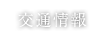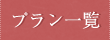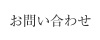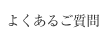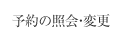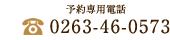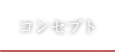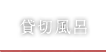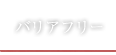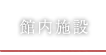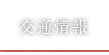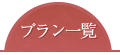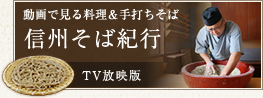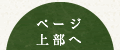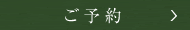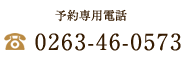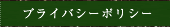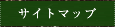最近よくテレビで目にする、宿泊予約比較サイトや広告。ふと思うのが、「あれ?同じホテルでも日にちによって料金がすごく違うなあ」ということ。特に、私たち宿泊施設の側から見ると、「なんでこの日だけこんなに高いの?」とか、「この部屋が突然安くなった?」という変化が気になったりします。
そこで今回は、宿泊業界で近年話題になっている「レベニューシステム(Revenue Management System:略してRMS)/レベニューマネジメント」と呼ばれる仕組みについて、できるだけわかりやすくご紹介します。私自身もこのシステムの存在をかなり前から知っており、ベータ版を試用したこともあります。大規模な宿泊施設には「なるほど、こういう場面で生きるなあ」と感じた経験もあります。とはいえ、当館のような中小規模の温泉旅館としては現在のところ導入の予定はございませんが、「こういう料金の変動の背景がある」ということを宿泊業として知っておくことは、実はとても大切だと考えています。
それでは順を追って、「そもそもレベニューシステムって何?」から、「導入が多いホテルチェーンの事情」「料金が高騰した背景」「当館としての考え」まで、一緒に見ていきましょう。
レベニューマネジメント(レベニューシステム)とは
まず、言葉から整理しておきます。
「レベニューマネジメント(Revenue Management)」とは、ざっくり言うと「限られた資源(=ホテルだと“部屋”)を、需要(お客さまの予約希望など)に応じて、最適な価格・最適な量(部屋数)で販売し、売上を最大化するための仕組み」です。
宿泊施設では「同じタイプの部屋」を使い切ってしまえば、それ以上売ることができない(=“売れないまま時間が過ぎるとその部屋は“消えてしまう”=品切れ・あるいは時を過ごしてしまう)という特性を持ちます。この「売れ残りやすい・時間とともに価値が減っていく」という性質が、レベニューマネジメントが宿泊業にフィットする大きな理由です。
これを支える仕組みとして、昨今は「レベニュー管理用のシステム(Revenue Management System:略RMS)」というソフトウェアやAIツールも使われるようになっています。例えば「過去の予約データ」「地域のイベント」「曜日・季節」「競合ホテルの料金」などを分析して、需要が高まる時期を予測し、「この日はこの価格で販売すべき」「こっちはもう少し下げた方が売れる」というような“価格指針”を出します。
もう少し噛み砕くと、ホテルの部屋という商品には次のような特徴があります。
- 例えば100室あるホテルなら、その100室分が“1泊分のストック”です。
- その1泊分を「いくらで」「何室売るか」を決めなければならない。
- 当日・直前になって部屋が残っていれば利益を取りそこねるかもしれないし、逆に料金を下げすぎると“売れてよかったけれど利益が少なかった”ということにもなります。
- さらに、予約が入るまでの時間、季節・曜日・イベント・天候などによって“需要(=予約希望)”が変動します。
- ですから、「どういう日に」「どのくらいの価格を」「何部屋販売するか」をデータに基づいて判断することが、近年は“普通”になっています。
このような意味で、レベニューマネジメントおよびそれを支えるシステム(RMS)は、ホテルの料金設定(room-rate)を“固定の定価+少し割引”という従来型から、「時期・需要に応じて動的に変化する価格」に変えていくものと言えます。
なぜ外資系ホテルチェーン・大手ビジネスホテルチェーンに多く導入されているのか
次に、「なぜ特に外資系のホテルチェーンや大手ビジネスホテルチェーンでこの仕組みが多く導入されているのか」を、当館の視点も交えて整理します。
まず、導入が多い背景として以下の点が挙げられます。
(1)部屋数・部屋タイプが多く、データを取りやすい
外資系ホテルチェーン、大手ビジネスホテルチェーンでは、全国・あるいは海外にも展開しており、部屋数が数百室ある施設や複数施設を運営しているケースが多いです。多数の予約データや複数の部屋タイプ・販売チャネル(直接予約、OTA、法人契約など)を扱っているため、RMSの導入によって「データを活かしやすい/メリットを出しやすい」という構図があります。
(2)販売チャネル・価格変動への対応力がある
大規模チェーンでは、価格や在庫を細かく操作できる体制・システムが整っている場合が多く、需要予測・価格最適化をシステムで支援することが効果的です。また海外からの宿泊(インバウンド)や出張・団体など、需要の幅が広い宿泊需要を持っているため、「単純に定価+割引」だけでは最適化しづらいという事情があります。
(3)グローバルな競争・市場変動に敏感
外資系チェーンは、世界各地のホテルと比較・分析されることも多く、競合ホテルの動き・国際観光動向・為替・イベントなどの影響を受けやすいです。こうした変動要因をデータでキャッチすることが、システム導入メリットの一つになります。
このような理由から、ホテル業界では「RMSを使って価格を動かす」という考え方が、外資系や大手チェーンで先行してきたわけです。実際、システム提供企業の紹介サイトでも「ホテル用レベニューマネジメントソフトウェアを活用して利益を最大化する」という文言が並んでいます。
私自身、宿泊業界に身を置いている中で「この仕組み(レベニューマネジメント)を、ホテルチェーンさんが導入している」という話をかなり前から耳にしていました。また、実際に“ベータ版”を試してみた経験もあります。そこでの感触として、「同じ部屋タイプを大量に持っていて、かつ曜日や季節で需要が大きく変わる施設にとっては非常に有効だ」と感じました。
――例えば、首都圏のビジネスホテル。平日は出張・会議で満室近く、土日・祝日は観光需要で変動が大きい。また、東京や大阪では大型イベント(スポーツ大会・国際会議・観光ピーク)などで“あっという間に予約が埋まる”というケースが想定されます。こういう施設こそ「この日は一気に料金を上げて利益を取る」「この時期は少し下げてでも稼働を上げる」という動きが反映しやすいのです。
そういう意味で、当館のような“部屋数が少なめ”、“同じ部屋タイプが少ない”、“宿泊+食事+温泉というパッケージ要素が強い”旅館では、導入を慎重に検討せねばならない、という実感が私にはあります。
「AIが宿泊料金をどのように算出しているか?」
次に、少しだけ“裏側”をのぞいてみましょう。もちろん実際の各システムの詳細アルゴリズムはベンダー毎・ホテル毎に異なり企業秘密も多いため、「こういう要素を見ている/こういう原理で動いている」程度にご理解ください。
(1)データ収集・変数設定
まず、システムは大量のデータを収集・分析します。例えば次のようなデータ:
- 過去の予約履歴:何日前に予約が入ったか、キャンセル率、延泊率、滞在日数など。
- 部屋タイプごとの販売実績:標準室/和室/スイートなどで、価格と予約数の相関関係。
- 季節・曜日・祝祭日・イベント情報:例えばスポーツ大会・学会・カウントダウン・観光シーズン・平日 vs 週末。
- 競合ホテル・類似ホテルの料金動向:同じ地域・同じクラスのホテルがどう料金を変えているか。
- 販売チャネル:直販・OTA(オンライン旅行代理店)・法人契約など、チャネルによって支払意欲・手数料率が異なります。
- 外的要因:天候、交通アクセス、観光動向、インバウンド(海外からのお客さま)など。
こういった要素を「この日にどれくらいのお客さまが来るか?」「この部屋タイプならどれくらいの価格までお客さまが払ってくれそうか?」という予測モデルに入力していきます。
(2)需要予測・価格弾力性の推定
次のステップは、「この日・この部屋タイプ・このチャネルで、どれくらいの需要があるか」を予測することです。言い換えると、「もし料金をこのくらいに設定したら、何室売れるか」という“売れ行き予測”を出します。
また、「お客様がどのくらい価格の変化に反応するか(価格を下げればどれだけ予約が増えるか/料金を上げればどれだけ落ちるか)」を推定する“価格弾力性”も重要です。たとえば、「同じホテル・同じ部屋タイプでも、料金を10%上げたら予約数が5%減る」という具合です。このようなモデルがあると、「料金を上げても利益が出るか?」「料金を下げて稼働を上げた方が結果利益が出るか?」という判断ができるようになります。
(3)最適価格・最適在庫数の算出
予測が出たら、システム(またはそれを活用する担当者)は「どの価格で何室販売するか」を決めます。ここで「最適価格」が算出され、「この価格なら利益が最大化される可能性が高い」という結論に至ります。また、「どの料金プランを優先すべきか(取消料あり/なし、前日予約可/不可、長期滞在割引など)」といった在庫・プラン管理も行われます。
このようにして、日々・時間帯・チャネル・部屋タイプ別に“動的な料金(ダイナミックプライシング)”が設定され、自動・半自動で価格が変わっていきます。例えば「あと30日後の平日」「あと10日後の土曜日」「あと3日後の満室近い日」などでそれぞれ料金が変わっているわけです。
(4)モニタリング・修正・最適化
また、料金を出して終わり、ではありません。システムや担当者は実際の予約の動きを常にモニタリングし、「予測と実績がどれくらいズレたか」「競合が料金を下げてきたか」「キャンセルが意外に多かった/少なかったか」などをチェックし、モデルを修正していきます。これを繰り返すことで、次回以降の最適化が進みます。
このような流れで「AI(あるいは高度なアルゴリズム)+データ+販売判断」が宿泊料金の設定に使われており、結果として「同じ部屋タイプでも日にち・予約タイミング・販売チャネルによって料金が大きく変わる」状況が生まれているのです。
私自身の経験・感じたこと
ここまで説明すると「ふーん、なるほど」と思われるかもしれませんが、私自身がこの仕組みに対して感じたことを、宿泊業・旅館経営という立場から少しお話します。
まず、私はこのレベニューマネジメントという概念を「かなり前から知っていた」ことを改めて触れておきます。宿泊業界では、「ピーク日の料金をグッと上げる」「閑散期に料金を抑えて稼働を上げる」という動き自体は昔からありました。ただ、それを“システム・AIを使って自動化・細分化”するということが近年さらに進化してきた、という印象です。
そして、国内ベンダーの提供するRMSがはしりの頃、ベータ版のRMSを実際自分も“試しに使ってみた”ことがあります。そこで感じたのは次のようなことでした。
- 同じ部屋タイプ(例えば「スタンダードシングル」など)をたくさん持っている施設では、料金を少し動かすだけで「数室分の売れ行き」が大きく変わるため、収益に対するインパクトが比較的大きい。
- 逆に、部屋数が少ない・部屋タイプのバリエーションが多い・宿泊+食事+温泉という付加価値が強い旅館形態では、「単純に“部屋のみ”で価格を変える」ことに限界や慎重さを感じた。例えば、料理内容を含むパッケージ料金だと“部屋料金だけ変えればよい”という構図になりづらいからです。
- また、料金を細かく変動させると、宿泊者の「“このホテル=定価がある”」という期待とずれる可能性があり、「値上げされたように感じて印象が悪くなる」リスクもあると感じました。
- その意味で、「需要変動が読みやすい時期」「複数の部屋タイプ・販売チャネルがあるホテル」「短期滞在が主流」という環境において、この仕組みはより“効く”な、という印象を持ちました。
こうした経験から、私としては「同じ部屋タイプを多く持つ大規模施設向きだと感じた」というのが率直な感想です。
「東京五輪・京都オーバーツーリズム/ホテル料金高騰」との関係性
ここで少し具体的な話に移ります。数年前、私たちもニュースで見ていましたが、例えば「東京五輪(2020年東京オリンピック)」「京都のオーバーツーリズム(観光客数が急増してホテル需要が急拡大)」といった話。これらの背景には、実はこうしたレベニューマネジメントの仕組みが関係していると、私は考えています。
具体的に整理すると:
- 東京・京都といった観光需要・宿泊需要が非常に高い都市においては、「この日に泊まりたい!」というお客様が多く、部屋が早く埋まりやすい。
- また、同時に多くのホテルが「イベント日・観光ピーク日」に備えて稼働を上げようとする。
- こうした環境では、RMSを導入しているホテルが「需要予測」「競合料金」「チャネル状況」などを見て、ピーク日の料金を通常よりかなり高く設定することが可能・実際行われている。
- 結果として、「東京や京都のホテル料金」がニュースになるほど“高騰”する、という現象が生まれたと考えられます。
つまり、単に「観光客が増えたから料金が上がった」という側面だけでなく、「ホテル側がRMS等を活用して、需要が高まる日=料金を上げるタイミングを捉えていた」ことが料金高騰の一因になっているのではないか、と私は感じています。
この観点は、宿泊業に従事する者として見逃せない視点です。需要変動を“読み”、料金を“動かす”という動きが、現代の宿泊マーケットでは日常化しているといえるでしょう。
「1泊2食付き」の料金体系とは相性が良くないという視点
さて、さらに掘り下げて言うと、宿泊料金の変動・最適化という流れについて「どんな料金体系と相性が良いか/良くないか」という観点も重要です。そして、私たち旅館経営者として考えると、特に「1泊2食付き」のような宿泊+食事(+温泉など)を含むパッケージ型プランとは、必ずしも相性が良いとは言えない、という結論に至っています。
その理由を整理します。
- 料金に“料理代金”や“温泉・サービス”が含まれているため、部屋だけの可変性が低い
ビジネスホテルのように「部屋のみ」「部屋+朝食」という分かれ方であれば、料金を比較的自由に変えやすいですが、旅館の場合は「部屋+夕食+朝食+温泉」というセットが多いため、料金の中身が複数のコスト要素(食材費・調理人件費・サービス費)と密接に結びついています。したがって、単純に部屋料金を上げれば良いという構図になりづらいのです。 - お客様の支払意欲・期待値が“宿泊+食事体験”に向いている
旅館の場合、料理・おもてなし・温泉という“非可視価値”が強く、お客様の支払意欲も「体験に対して」という側面が大きいです。このため、「同じ部屋タイプでも日にちによって大きく料金を変える」ことが、お客様にとって「なんだか高く感じる」「前回泊まったときより高くなった」という印象を生みやすく、ブランド・信頼の観点から慎重にならざるを得ません。 - 部屋タイプ・販売チャネル・滞在形態の幅が限られている場合が多い
旅館では「和室」「和洋室」「露天風呂付き客室」など数タイプあっても、ビジネスホテルのような「スタンダード/デラックス/スイート」「シングル/ツイン/ファミリー」などの豊富なタイプ・シングル販売チャネルが少ない場合があります。このため、RMSが得意とする「大量のデータで部屋タイプ・チャネル別に細かく価格を変える」構図が弱くなります。
以上のような理由から、私たち旅館業の立場では「1泊2食付き」の料金体系とは、レベニューマネジメント(特に動的価格変動を前提とするモデル)との相性が“良くない”という見方を持っています。実際、前回の記事(「最近よく見るトリバゴのCMを見て思うこと」)でも触れたとおり、料理代金を含めての料金変動は難しいと考えています。
「宿泊料金(特にインバウンド)は相場連動性になりつつある」&「定価という概念がなくなりつつある」
さて、ここからは少しマーケット全体の動きを読み解く視点です。最近では、宿泊料金の設定において「定価」という概念が薄れてきており、むしろ“相場連動性”が強まっていると感じています。
まず、「インバウンド(海外からのお客様)」の増加・変化によって、ホテル料金がより“グローバルな需要・競合・比較”にさらされるようになっています。つまり、海外の旅行者がオンラインで検索し、比較し、支払意欲を持って予約するという流れが一般的になり、宿泊施設としても「どのくらいの価格なら海外のお客様が泊まるか」「競合国・地域のホテルがこの価格ならこちらもこの価格帯か」という視点が必要です。
このような背景もあって、宿泊料金は「このホテルの定価はいくら」という固定観念から、「この地域・この日・この部屋タイプ・この販売チャネルで、このくらいの価格が出ていればうちもこれくらい出そう」という“相場連動型”の考え方に変わってきていると思います。まさに「定価という概念がなくなりつつある」と言っても過言ではありません。
先に説明したレベニューマネジメントの仕組みがこれを支えていて、「需要が高ければ価格を上げる」「需要が低ければ価格を下げて稼働を上げる」というサイクルが常態化しています。また、OTAや比較サイト、口コミサイト、予約チャネルの多様化によって、料金情報が可視化されており、宿泊者側も「今この日に泊まるならこのくらい」という“市場感覚”を持つようになってきています。
このような料金動向・市場感覚の変化は、当館のような旅館にも無視できない流れです。たとえば、「あのホテルではこの日にこの価格出しているから、うちもこれくらい出すか」「あの日ならこの価格であっても納得されるだろうか」という思考が、今や宿泊施設側にも必要になっています。
当館としての考え:なぜ今のところ導入しないのか
ここまで説明してきたような「レベニューマネジメント/レベニューシステム」の仕組みとトレンドを踏まて、改めて私たち「ホテル玉之湯」が“現在導入を考えていない”理由を、率直に整理します。
- パッケージ型(宿泊+食事+温泉)のサービス構成
当館は、温泉旅館として「宿泊+夕食+朝食+温泉」という体験型プランを基本としています。料理内容・温泉・旅館らしいおもてなしが大きな価値を持つため、部屋料金だけを大きく動かすという構図がそぐわないと考えています。上に述べたように、料理代金という固定コスト・サービス内容が大きいため、単純な動的価格変動は慎重を期す必要があります。 - 部屋タイプ・規模・販売チャネルの特性
当館は部屋数・部屋タイプともに大規模ホテルに比べて少なめであり、「同じ部屋タイプを多数持つ」構図ではありません。また、販売チャネルも主要なOTAと直販を含めておりますが、チェーンホテルのように多チャネル・多タイプ・短期需要変動型という構造ではありません。こうした条件では、RMSの“効率性/効果性”が必ずしも最大化されるとは限らないと判断しています。 - 宿泊者との信頼・ブランド観の維持
料金を頻繁に変動させることは、“このホテル=定価がある”という宿泊者の感覚を揺るがす可能性があります。特に旅館という業態では、「いつ来てもこのクオリティ・この雰囲気・このおもてなし」という安心感が重要であり、料金の不透明・変動の激しさが宿泊者の印象を悪くしてしまうリスクを懸念しています。 - 当館のお客様層・滞在形態・予約プロセス
当館の多くのお客様は「ゆったり温泉に泊まる」「料理をゆっくり楽しむ」「非日常を味わう」という滞在形態です。このため、「直前予約」「短期ビジネス泊」「変動が激しいチャネル主体」という構図ではありません。むしろ、通常のペースで宿泊されるお客様を大切にしています。こうした事情から、「高度な需要予測/価格弾力性モデル」を動かす導入効果が限定的だと感じています。
以上の理由から、「今のところ」当館としてはレベニューマネジメントシステムの導入予定はございません。しかしながら、あくまで「導入しない」ではなく「導入を慎重に検討し、当館にとって最適な形を考える」というスタンスです。宿泊業界全体の料金がこういうシステムによって変動しているということを、私たちも知っておかなければならない、というのが私の考えです。
宿泊料金の変動時代を知っておく
最後に、この記事を通して皆さまにお伝えしたいことを、もう一度整理しておきます。
- 宿泊料金は「定価+少し割引」という昔ながらの枠から、「需要・部屋数・販売チャネル・時間によって変動する」仕組みに変わってきています。
- この変動の背景には、レベニューマネジメント(Revenue Management)という考え方と、それを支えるシステム(RMS)が深く関わっています。
- 外資系ホテルチェーン・大手ビジネスホテルチェーンでは、部屋数・部屋タイプ・販売チャネルが多く、需要変動が読みやすいため、この仕組みが早くから導入されてきました。
- 「AIがどう算出しているか?」というと、膨大なデータ(過去予約・イベント情報・競合料金など)を分析し、需要予測・価格弾力性分析・最適価格・在庫管理・モニタリングという流れで動いています。
- 私自身の経験からも、「同じ部屋タイプを多く持つ大規模施設向き」だと感じています。一方で、旅館のような「宿泊+食事+温泉」のパッケージ型プランとは、必ずしも相性が良いとは言えないという見方があります。
- 現在では、宿泊料金が「相場連動性」を持ち始め、「定価」という概念が薄れてきています。これはインバウンド増加・オンライン予約普及・比較サイトの発展などの影響です。
- 当館では現段階でレベニューマネジメントシステムを導入予定ではありません(というよりできない)が、このような料金変動の仕組み・マーケットの流れを知ることは、宿泊施設として重要であると認識しています。
- 最後に、宿泊をご検討されるお客様にとっても「この日は価格が高め/この日は価格が少し抑えめ」という背景には需要・チャネル・ホテル側の販売戦略という“見えない仕組み”があるということを知っておいていただくと、料金を見たときの印象も少し変わるかもしれません。
旅館という業態は、「立地」「温泉」「料理」「おもてなし」といった“体験型”価値が強く、料金だけで比較されることが必ずしも本質ではありません。とはいえ、宿泊料金の算出背景がこうした先進的な仕組みによって変わってきているということを、私たちも「知っておく」こと、そしてお客様にも「知っていていただく」ことは、これからの宿泊業界において大きな意味を持つと感じています。
ホテル玉之湯 内藤幸宏より
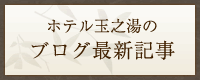

2026年1月14日


2025年12月28日
【年末のご挨拶】本年もホテル玉之湯をご愛顧いただきありがとうございました


2025年12月15日
🌟 松本市大名町イルミネーション2025–2026 〜冬の夜を彩る光のストーリー〜


2025年12月15日


2025年12月9日

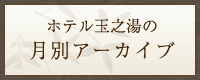
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (5)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (10)
- 2025年9月 (3)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (7)
- 2025年5月 (26)
- 2025年4月 (26)
- 2025年3月 (12)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (7)
- 2024年12月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (8)
- 2023年9月 (7)
- 2023年5月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (7)
- 2022年2月 (8)
- 2022年1月 (13)
- 2021年12月 (30)
- 2021年11月 (5)
- 2021年6月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (4)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (4)
- 2020年3月 (20)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (5)
- 2019年2月 (5)
- 2018年11月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (5)
- 2018年1月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (5)
- 2017年3月 (2)
- 2017年1月 (6)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (1)
- 2015年4月 (2)
- 2015年2月 (3)
- 2015年1月 (3)
- 2014年12月 (16)
- 2014年11月 (26)
- 2014年7月 (1)
- 2012年11月 (2)
- 2010年12月 (1)
- 2010年11月 (4)
- 2009年12月 (16)
- 2009年11月 (11)
- 2008年12月 (20)
- 2008年11月 (10)
- 2007年12月 (11)
- 2006年12月 (16)
- 2006年7月 (1)
- 2006年4月 (14)
- 201年11月 (1)